
機能強化型在支診・在支病
機能強化型在支診・在支病の施設基準
1.在支診・在支病の要件に以下を追加する(単独型)
・在宅医療を担当する常勤医師3人以上
・過去1年間の緊急の往診実績10件以上
※「緊急の往診」とは、緊急・夜間・休日・深夜の往診を指す
・過去1年間の看取り実績4件以上または、過去1年間の15歳未満の超・準超重症児に対する総合的な医学管理の実績4件以上
2.複数の医療機関が連携して1の要件を満たすことも可能とするが、連携する場合は、以下の要件を満たすこと(連携型)
・患者からの緊急時の連絡先を一元化
・患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関で月1回以上の定期的なカンファレンスを実施している
・連携する医療機関数は10施設未満
・病院が連携に入る場合は、200床未満の病院に限る
・連携に参加する各医療機関が、過去1年間の緊急往診件数4件以上と、看取り件数2件以上または、15歳未満の超・準超重症児に対する総合的な医学管理の実績2件以上を満たすこと
厚生労働省「主な施設基準の届出状況等」による施設数(2016年7月時点)
・機能強化型在支診は、2914施設(うち連携型は2725施設)
・機能強化型在支病は、472施設(うち連携型は317施設)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

機能強化型在支診・在支病
機能強化型在支診・在支病
・在宅医療の普及には24時間いつでも患家を訪問できる体制が不可欠との考えから、2012年度診療報酬改定で、一般の在宅療養支援診療所(在支診)、在宅療養支援病院(在支病)ができた
・複数の医師を擁し、地域の核となる在支診・在支病を評価したもので、在支診同士もしくは在支病と連携して要件を満たしても、連携型として同等の評価が得られる
・機能強化型の中にも緊急往診や看取りをあまり行っていないケースが目立ったため、2014年度診療報酬改定で緊急往診と看取りの実績の要件が厳格化された
・2018年度改定では、居宅や施設での看取り体制の整備を図るため、看取りにかかる評価が充実された
・在宅看取りの実績に関しては、あらかじめ聴取した患者や家族の意向に基づき自院または連携医療機関に入院し、7日以内に死亡した場合も実績に算入できるようになった
・見直しにより、看取りの実績の要件をクリアしやすくなることで、機能強化型在支診・在支病を届け出る医療機関が増える可能性がある
・中重度の在宅患者のほとんどは、医療費負担が軽減される重度心身障害者医療費助成制度の対象となるため、自己負担への影響はあまりないと考えられる
・比較的軽度の在宅患者については、費用負担が問題となる可能性がある
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅療養支援病院
在宅療養支援病院(在支病)
→24時間465日体制で地域の在宅医療を支える病院を評価する制度
・以前は半径4km以内に診療所がある場合は届け出できなかったが、2010年度改定で、200床未満の病院についてこの制限が撤廃された
・これを機に、在支病(機能強化型を含む)の数が増え、2016年7月時点で1135施設に達した
・在支診と同じ施設基準を満たして届け出れば在支病となることができ、在支診と同じく、往診料の加算、在宅ターミナルケア加算、在総管、施設総管などにおいて高い点数を算定できる
在支病の主な届け出要件
1)許可病床数200床未満の病院
2)在宅療養を行っている患者に緊急に往診ができる体制を整え、緊急入院が必要な場合に入院できる病床を常に確保している
3)患者の求めに応じて、自院または訪問看護ステーションとの連携により、24時間往診・訪問看護ができる体制を常に確保している
4)往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること
在宅療養実績加算
・「在宅医療を担当する常勤医師3人以上」の要件を満たせないため機能強化型を届け出ていない在支診・在支病で、看取りなどの実績が十分ある場合には在宅療養実績加算を算定できる
・同加算は緊急往診と看取りの件数に応じて2段階に設定されている
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所(在支診)
→高齢者が住み慣れた家庭や地域で療養しながら長く生活できるよう、また、身近な人に囲まれて在宅で最期を迎えることも選択できるよう、診療報酬制度上に設けられて仕組み
・在支診として届け出た診療所は、往診料の加算、在宅ターミナル加算、自宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)、退院時共同指導料1などで、一般の診療所より高い点数を算定できる
在宅療養支援診療所(在支診)の主な届け出要件
1)診療所であること
2)その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供している
3)患者の求めに応じて、自院または他の医療機関、訪問看護ステーションと連携し、24時間往診・訪問看護ができる体制を確保している
4)3)の患者に対して、24時間往診・訪問看護を行う担当医師・担当看護師などの氏名、担当日などを患家に文書で提供している
5)緊急入院受け入れ体制を確保している(他の医療機関との連携による確保でよい)
6)地方厚生(支)局長に年1回、在宅看取り数などの報告をしている
7)直近1ヶ月の在宅患者割合が95パーセント未満であること
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

同一建物居住者
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)と往診料
・同一建物居住者以外と同一建物居住者の2種類の点数があるが、この基礎となるのは訪問人数
・居住場所によらず、1日に患者1人のみ診療した場合、「同一建物居住者以外」の点数(830~833点)を算定できる
・施設や集合住宅などの居住者を同一日に2人以上診察した場合、「同一建物居住者」とみなされ、178~203点を算定する
・同じ建物内で2人以上診察すると往復の手間と費用が省けるため、その分、減算される
・末期の悪性腫瘍と診断した後に訪問診療を始めた日から60日以内の患者、死亡日から遡って30日以内の患者などは同一建物居住者とみなさず、「同一建物居住者以外」の点数を算定する
・「同一患家」で同一日に2人以上の患者に訪問診療を行った場合、1人目は在宅患者訪問診療料を算定し、2人目以降は初診料または再診料、外来診療科および検査や投薬、処置などの特掲診察料のみ算定する
・この場合、1人目は在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者以外」の点数を算定する
・同一建物において、同一日に「同一患家」で2人以上を訪問診療し、さらに別の患家に訪問診療するなど、同一建物で2ヶ所以上の患家に訪問診療した場合、全員を「同一建物居住者」とする
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
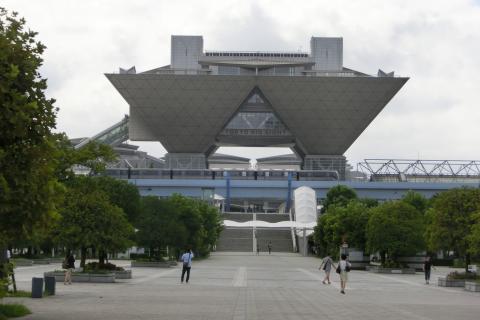
同一建物居住者
同一建物
→施設やマンションなどの集合住宅
・同一敷地内や隣接地に集まった各棟や渡り廊下でつながった棟は別の建物として扱う
同一患家
→同一世帯(マンションの一室や一軒家)に複数の患者が同居する場合
・有料老人ホームでも、同一患家とみなすのが適当な場合(夫婦同室など)がある
・往診料、在宅患家訪問診療料には、同一患家の概念が適用される
同一建物居住者
→1ヶ所の医療機関が同一日に、訪問診療や訪問看護などを、同一建物の患者2人以上に行った場合、「同一建物居住者」として扱う
・同一世帯に複数の患者が同居する場合、「同一患家」として扱う
診療報酬上、同一建物居住者として扱われる施設、サービスの利用者
1)老人福祉法が規定
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
2)介護保険法が規定
・短期入所生活介護(介護予防含む)
・グループホーム(介護予防含む)
・小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護(介護予防含む、宿泊サービス利用時に限る)
3)その他
・マンションなどの集合住宅(サービス付き高齢者向け住宅含む)
減算
・訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護などの訪問系サービスにおいて、同一建物に住む月20人以上の利用者に介護サービスを提供している場合や、事業所と同一敷地または隣接地の建物に利用者が住んでいる場合など、基本報酬が10~15%減算される
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
在宅患者訪問診療料の算定のポイント
8)在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、有料老人ホーム等に併設される医療機関が、その施設の入居者に訪問診療を行った際に算定する
・定期的な訪問診療の場合はイ、他の医療機関の依頼による訪問診療の場合はロを算定する
9)医師の配置義務がある施設の入居者は、基本的に在宅患者訪問診療料の算定対象外となる
10)在宅で死亡した患者(往診や訪問診療の後、緊急搬送などで24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を行った場合、在宅ターミナルケア加算を算定できる
・ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者本人や家族などと話し合いを行い、本人の意思決定を基本に他の関係者との連携の上対応する
11)看取り加算は、事前に患者または家族などに対して療養上の不安などを解消するために十分な説明と同意を行った上で死亡日に往診または訪問診療を行い、患家で看取った場合に算定する
12)死亡診断加算は、死亡日に往診や訪問診療を行い、患家で死亡診断した場合に算定する
13)往診の日の翌日の訪問診療の費用は原則算定できないが、在宅療養支援診療所やその連携医療機関、在宅療養支援病院は算定できる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
在宅患者訪問診療料の算定のポイント
5)在宅患者訪問診療料は、継続診療の必要のない者や通院可能な者に対して安易に算定してはならない
・独歩で家族・介助者の助けを借りずに通院できる者などには算定できない
・通院による療養が困難か否かは医師の判断による
6)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1は、1人の患者に対し1つの医療機関の医師の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、初診料の算定日には算定できない
※但し、在宅悪性腫瘍患者挙動指導管理料を算定する場合に限り、患者1人に2つの医療機関の医師が、1日につき各1回に限り算定できる
7)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2は、他の医療機関の依頼により、診療を求められた傷病に対して訪問診療を行った場合、求めがあった日を含む月から6ヶ月を限度として算定する
・同一患者について、その診療科の医師でなければ困難な診療や、既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病についての診療の求めが新たにあった場合は、その求めがあった日を含む月から6ヶ月さらに算定できる
・厚生労働大臣が定める傷病等の患者については6ヶ月を超えて算定できる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
在宅患者訪問診療料の算定のポイント
1)在宅患者訪問診療料は、在宅で療養している患者で通院が困難な者に対し、同意を得て計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療した場合に、当該患者1人につき週3回を限度に算定する
・「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合患者、急性憎悪などにより頻回の訪問診療が必要とされる患者には制限がない
2)訪問診療時には、患者や家族などの署名付きの同意書を作成して診療録に添付しなければならない
・訪問診療計画や診療内容の要点、診療時間、診療場所も診療録に記録する
・他の医療機関の求めに応じて紹介患者に訪問診療を行った場合は、診療を求められた傷病も記録する
3)在宅患者訪問診療科(1)の「同一建物居住者の場合」は、医師が同一日に複数の同一建物居住者を訪問診療した場合に算定する
※但し、以下の患者は同一建物居住者として数えない
・往診を実施した患者、末期悪性腫瘍の診療後に訪問診療を始めた日から60日以内の患者、死亡日から遡って30日以内の患者
4)医療機関が診療に基づき、患者の急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に訪問診療した場合は、週4回以上、在宅患者訪問診療料を算定できる
※但し、月1回に限り、当該診療の日から14日以内の訪問診療について14日を限度とする
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
往診料算定のポイント
7)往診に要した交通費は患家の負担としてもよい
8)数事業所の衛生管理医をしている保険医が衛生管理医として毎日または定期的に事業所に巡回した再、当該事業所において常態として診療を行う場合は、3)と同様である
9)緊急往診加算は、医療機関の勤務時間でもっぱら診療に従事している時間内に、患家またはその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する
10)緊急往診加算の対象となる緊急な場合とは、患者または現にその看護にあたっている者からの訴えにより速やかに往診しなければならないと判断した場合のことをいい、具体的には往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症などが予想される場合をいう
・2018年度改定で、医学的に終末期であると考えられる患者でも緊急往診加算を算定できるようになった
11)往診料については、夜間・休日、深夜、緊急などの加算はあるが、時間外加算はない
12)「18時から翌朝8時」に往診した場合は、夜間休日加算
・「22時から翌朝6時」に往診した場合は、深夜往診加算を算定する
13)日曜及び国民の祝日に関する法律第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日、31日に往診したばあい、夜間・休日往診加算を算定する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
往診料算定のポイント
1)在宅医療の距離的制限については、往診の範囲が直線距離で16km以内と定められている
・患家周囲に往診可能で適当な医療機関がないなどの特別な条件がある場合は除かれる
2)往診料は患家の求めに応じて患家を訪問して診療を行った場合に算定できるもの
・定期的または計画的に患家または他の医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない
3)特定の被保険者の元萌に応じるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期または不定期に事業所などへ赴き、患家を診療する場合は、往診料として取り扱うことは認められない
4)往診または訪問診療を実施した後に、患家またはその家族などが単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料、外来診療料は算定できない
5)往診料には同一建物居住者の概念はない
・マンションはアパートなど、個々の住居が独立している集合住宅では、それぞれの住居において往診料を算定できる
6)同一の患家または有料老人ホームなどであって、その形態から当該ホーム全体を同一患家とみなすことが適当である場合において、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料を算定せず、初・再診料などを算定する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
往診と訪問診療
往診
→患者の求めに応じて患家を訪問すること
訪問診療
→定期的、計画的に患家を訪問して行うこと
往診料
→患者または家族等が医療機関に電話等で直接往診を求め、医師が必要性を認めて可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できる
※可及的速やかにとあるが、往診の日時については依頼の詳細に応じて医師が医学的に判断することとされた
在宅患者訪問診療料
→通院が困難な者に対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に週3回を限度に算定できる
※但し、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する患者の場合は回数制限はない
2018年度改正で訪問診療料は(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分された
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
・有料老人ホーム等に併設される医療機関以外の医療機関が訪問診療を行った場合に算定する
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
・有料老人ホーム等に併設される医療機関が、その施設の入居者に訪問診療を行った際に算定する
※訪問診療料ではこれまで、一人の患者に対して1ヶ所の医療機関しか算定できないルールがあったが、2018年度改正により、この取り扱いが見直され、他の医療機関の依頼により訪問診療を行った場合の点数が新設された
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療の診療報酬
在宅医療の基本報酬
・在宅患者訪問診療料
・往診料
・在宅時医学総合管理料(在総管)
・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)
※上記の基本報酬の中でも、在宅患者訪問診療料と往診料は患家で診療した都度、出来高で算定する点数なのに対し、在総管と施設総管は患家に24時間365日対応できる医療機関の体制を評価した点数で、患者1人につき月1回算定する点が異なる
※在総管と施設総管は、24時間365日耐性を整えて定期的な訪問診療を月1回以上行うことが要件となっている
患者の状態に応じた報酬など
・基本報酬の他に患者の状態に応じて
1)在宅ターミナルケア加算
2)在宅療養指導管理料
3)在宅患者訪問点滴注射管理指導料
4)薬剤料や特定保険医療材料料
5)指示書や同意書といった書類関連や連携対応などに関する点数
※具体的には、訪問看護指示料、退院時共同指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料などがある
診療報酬点数上の分類
・診療報酬点数上でみると、基本診療料の他に
1)在宅患者診療・指導料(往診料、在総管など)
2)在宅療養指導管理料(在宅酸素療法指導管理料など)
3)薬剤料(注射薬など)
4)特定保険医療材料費(創傷被覆材など)
5)その他
という形に分類することができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

医療保険制度の仕組みと窓口負担
公的医療保険制度
→加入者が収入に応じて保険料を出し合い、加入者やその家族などが医療が必要な状態になった際、患者の窓口自己負担分を除いた医療費をそこから捻出する仕組み
・加入者が出し合った保険料は保険者が管理し、患者がその都度医療費を支払う
・年齢や職種などによって保険の種類が決まり、それによって患者の窓口負担も異なっている
窓口負担割合
→患者が保険医療機関などにかかった際、治療に要した医療費全体のうち、当該機関の窓口で患者自身が支払う医療費の割合
70歳未満の人
・外来、入院にかかわらず医療費の3割を窓口で負担すれば治療が受けられる
・残りの7割は保険者が負担する
70歳以上75歳未満の人
・2008年4月に1割から2割に引き上げられたが、国の特別措置により1割に据え置かれていたが、2014年度から見直され、同年4月以降に70歳に達した人は2割、既に70歳に達している人は1割とされた
※ただし、いずれの場合も、現役並みの一定所得がある人は3割となる
75歳以上の人
・2008年4月より、75歳以上(または65歳以上の寝たきり等の状態)の人については、一般の医療保険制度から切り離して独立させた「後期高齢者医療制度」が設けられた
・所得に応じて、自己負担額は1割または3割となる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療
カンファレンスに盛り込むべき情報
年齢
・介護保険の要支援・要介護認定を受けられるかどうかを確認する
1)40歳未満の場合
・介護保険の給付対象とならないため、障害者総合支援法の対象となり得るか否か検討する
2)40歳以上65歳未満の場合
・介護保険の第2号被保険者で、「特定疾病」により要介護状態となった場合、介護保険の給付対象となる
・該当しない場合は、障害者総合支援法の対象となり得るか否か検討する
3)65歳以上の場合
・介護保険の第1号被保険者となるため、要介護認定を受ければ、疾病に関係なく介護保険の給付対象となる
主病名
・在宅医療を行う原因となった病名を主病名として挙げるが、その他にも「特定疾病」「指定難病」などがあれば追加する
・「指定難病」に該当すれば、医療費の公費助成の対象となる
・「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当すれば、医療保険の訪問看護が利用できる
ADL
・ADLを確認することで、在宅医療の適応か否かを調べる
・在宅医療の対象は、通院困難な状態と主治医が判断した場合である
・身体障害者手帳の対象となれば福祉制度の利用が可能となる
・重度心身障害者医療の対象となれば医療費の公費助成が受けられる
医療処置
・「特掲診療料の施設基準等別表に挙げる状態等」に該当すると、長時間や複数名による訪問看護、1日複数回の訪問看護を受けられるようになる
居住場所
・患者の居住場所により、訪問診療や訪問看護などの提供の可否が異なる
・特別養護老人ホームの場合、訪問診療を提供できるのは末期悪性腫瘍か死亡日から遡って30日以内に限られる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療
在宅医療の対象となる患者
・保険診療上、在宅医療の対象は、「在宅で療養を行っている患者であって、疾病、傷病のため通院による療養が困難な者」とされている
・個々の患者が該当するか否かは、主治医の判断による
・在宅患者訪問診療料などについては、「少なくとも独歩で家族、介助者などの助けを借りずに通院ができる者などは算定できない」ことが通知されている
対象となる患者の居住場所
・保険診療上の「在宅で療養を行っている患者」には、自宅だけでなく、高齢者住宅や介護保険施設・事業所の入所者、利用者も含まれる
・医療機関の入院患者は対象外
・介護老人保健施設も基本的に保険診療の対象外で、併設医療機関以外の医療機関による往診料と在宅療養指導管理の材料加算の算定のみ認められる
※医師の配置が義務付けられている施設は基本的に対象外となる
・特別養護老人ホームに関しては、往診料のほか、条件付きで在宅患者訪問診療料などの算定が認められている
自宅以外で在宅医療の対象となる施設や住宅
1)特別養護老人ホーム
2)養護老人ホーム
3)軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
4)有料法人ホーム
5)サービス付き高齢者向け住宅
6)特定施設、地域密着型特定施設、外部サービス利用型特定施設
7)短期入所生活介護事業所
8)に認知症対応型共同生活介護事業所
9)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能居宅介護事業所
10)上記以外の社会福祉施設、障害者施設など
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

在宅医療
在宅医療を取り巻く各種制度
・在宅医療に関連する制度は、大きく分けて、「医療保険制度」、「介護保険制度」、「福祉制度」の3つがある
・在宅医による診療については、医療保険で規定される
・在宅医療の一翼を担う訪問看護、訪問リハビリテーションは、医療保険、介護保険の双方に報酬や人員基準などが規定されている
・福祉制度では、障害者などが医療費自己負担の軽減措置や障害福祉サービスなどを受けられる仕組みが整備されている
・在宅医療は、患者の自己負担が外来より高くなりがちであるが、福祉制度を効率的に使えば、患者の金銭面の負担軽減などを図り、在宅生活を継続しやすくなる
・在宅医療では、提供したサービスに支払われる報酬の体系も、外来・入院医療に比べて複雑である
地域包括ケアシステム
・厚生労働省が、2025年を目途に整備しようとしているもの
・交通手段を問わず、概ね30分以内に移動できる地域を「日常生活圏域」とし、その地域の要介護者や患者に医療、介護、住まい、生活支援サービスをトータルで提供する仕組みである
・これにより、高齢者は可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにすることを目指している
・2018年度診療報酬改定では、在宅医療の担い手となる医療機関を増やすため、加算が新設され、在宅看取りに対する評価が拡充されたり、報酬が見直された、
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

糖尿病
糖尿病の合併症
→急性合併症と慢性合併症とがある
急性合併症
・命の危険があり、十分な注意が必要である
糖尿病昏睡
→極度のインスリン不足により起こる
1)ケトアシドーシス性昏睡
・インスリン注射を忘れたとき
・感染症、外傷などで血液が極端な酸性に変化して起こる
2)非ケトン性高浸透圧性昏睡
・高齢者がのどの渇きに気づかず、著しい脱水状態に陥って起こる
治療と予防
・昏睡に至る前に、強い喉の渇きや多飲多尿、倦怠感、嘔吐、腹痛などがみられることが多い
※昏睡状態に陥った場合、大量のインスリン注射などの緊急処置をとらないと、命を落とす危険がある
慢性合併症
・血液中のブドウ糖により血管が傷つけられて発症する
・糖尿病自体と同じで、徐々に進行するため、初期には自覚症状がほとんどなく、気づいたときには深刻な状態まで進行していることがある
細小血管合併症
・全身を巡っている細い血管で起きる
・代表的なものは、糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症(3大合併症)
大血管合併症
・動脈硬化が進行して、血管の内側が細くなり、詰まりやすくなって起こる
・代表的なものは、脳卒中、心筋梗塞、狭心症
※糖尿病があって、心筋梗塞を発症すると、予後は非常に悪くなることがある
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

糖尿病
糖尿病が起こるメカニズム
→インスリンの分泌や作用が低下して、血液中のブドウ糖が慢性的に多くなるため起こる
ブドウ糖
・食事でとった炭水化物が、腸管で分解されてできる
肝臓
・腸管で吸収したブドウ糖を血管を通して全身へ送る
・余った分は蓄積する
脂肪細胞
・余ったブドウ糖は脂質として蓄えられ、必要に応じてブドウ糖に分解されてエネルギー源となる
筋肉
・ブドウ糖を筋肉細胞で取り込み、エネルギーとして消費する
膵臓
・インスリンを分泌
健康な場合
・インスリンの作用で血液中のブドウ糖の量がコントロールされている
糖尿病の場合
・インスリンが十分に作用しない
1)インスリン分泌量の低下
・分泌されるインスリンの量が少なくなる
・分泌が遅れる場合もある
2)インスリン抵抗症
・インスリンは分泌されているが、筋肉や肝臓で十分に働かなくなる
糖尿病の分類
1型糖尿病
・自分の細胞を異物としてみなして攻撃する自己免疫によって、膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンが分泌されなくなる
・小児期から青年期に発症することが多い
2型糖尿病
・インスリンの分泌量低下とインスリン抵抗症が重なって起こる
・中高年以上がかかる糖尿病のほとんどが2型糖尿病
・日本人の糖尿病の90から95パーセントを占める
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

糖尿病
糖尿病とは
→血液中のブドウ糖の濃度が慢性的に高くなる状態
・血液中のブドウ糖の濃度を血糖値という
・ブドウ糖は、食事でとった炭水化物が胃や腸などで分解されてできる
・腸管から吸収され、肝臓を経て血液の流れにのり、全身に運ばれる
・筋肉細胞に取り込まれてエネルギー源になり、余った分は肝臓や脂肪細胞に蓄えられる
・細胞への取り込みや肝臓での蓄積には、膵臓から分泌されるインスリンが関わっている
・インスリンの分泌や作用に障害が起こると、ブドウ糖の消費と蓄積が十分に行われなくなるため、血糖値の高い状態が続き、糖尿病になる
インスリン
・食事でとったブドウ糖がエネルギー源として使われたり、肝臓などに蓄積されるしくみを糖代謝という
・インスリンは糖代謝に関わるホルモンのひとつで、血糖値を下げる働きがある
インスリンが十分に働かなくなる主な原因
1)インスリン分泌量の低下
・膵臓からのインスリン分泌量が少ない場合
・遺伝的な体質が関係している
・日本人にはこの体質の人が多い
・食事のあと、分泌が遅れるため、インスリンが十分に作用しない場合がある
2)インスリン抵抗症
・インスリンが分泌されても、筋肉や肝臓で十分に作用しないことを、インスリン抵抗症という
・主な原因は、肥満による内臓脂肪の蓄積で、脂肪細胞からインスリンの働きを妨げる物質が多く分泌されるため
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

高血圧
高血圧の原因
1)加齢
・年齢が上がることで、血管の壁が厚くなったり、弾力が失われて硬くもろくなる動脈硬化による影響
・動脈硬化が進行すると、抹消血管抵抗が強まり、血液の流れが悪くなり、心臓は全身に血液を運ぶためより強い力で血液を送り出すようになるため
・血圧の高い状態が続くと、血管の壁には大きな負担がかり、その負担に負けないため血管の壁が厚くなり、さらに動脈硬化が進行する
2)食塩のとり過ぎ
・食塩をとり過ぎると、ナトリウムの摂取量が増えて血液中のナトリウム濃度が上がる
・血液中のナトリウム濃度が高くなると、血管内に周りの水分を引き込んだり、のどの渇きが誘発されて水分を多量にとるようになる
・それに伴って血液の量が増えるため、心拍数も増加して血圧が高くなる
3)交換神経の働き
・体中に張り巡らされた自律神経は、循環器や呼吸器、消化器など全身のさまざまな活動をコントロールして、交換神経と副交感神経から構成されている
・交換神経は、血液を上げる方向に働き、副交感神経は下げる方向に働くため交換神経が活発になると、血圧が上昇する
交換神経が血圧に与える影響
・心拍数を増やす、血管を収縮させる、血液の粘り気を高める、血圧を上げるホルモンの分泌を促す
4)ホルモンの働き
・交換神経の働きが活発になると、腎臓からレニンの分泌が増し、アンジオテンシンⅡが増加する
・アンジオテンシンⅡは、腎臓の上にある副腎を刺激してアルドステロン分泌を増し、心拍出量が増すため血圧が上昇する
5)肥満
・血糖を調整するインスリンの働きが低下するインスリン抵抗性があると、インスリンの分泌量は増すが、血液中のインスリン濃度があたり、高インスリン血症となる
・高インスリン血症になると、交感神経の働きが活発になり、血圧が上昇する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

高血圧
血圧を下げる7つのコツ
5)たばこと深酒をやめて動脈硬化を防ぐ
・喫煙習慣があると、血管が傷ついて動脈硬化が進行し、心筋梗塞などを招きやすくなる
・酒の飲み過ぎも血圧を上げ、脳卒中などのリスクを高めるため、適量を守ることが大切
6)疑問や不安は医師に相談しながら正しく服薬する
・薬を服用することで、ほぼ確実に血圧を下げることができ、生涯にわたって血圧を適切にコントロールすることも可能である
・疑問や不安があれば、医師に相談して解消し、前向きに治療に取り組むことが大切である
7)睡眠や、できるだけ同じ時間にとる
・睡眠時間が十分でないと、血圧が高くなりやすいことが分かっている
・睡眠は十分に確保することが大切
・毎日の起床時間と就寝時間をできるだけ同じにして、体内時計を整えると血圧が安定する
※高血圧について知ることが、治療を続けるモチベーションにつながる
・高血圧は自覚症状がほとんどないので、治療の必要性に疑問をもつ人も少なくありません
・薬を飲むことへの不安をもつ人もいるが、高血圧の薬は決して副作用が多いわけではない
・減塩や減量で薬が必要なくなることもある
・高血圧の怖さをしっかりと理解し、治療へのモチベーションを高めることが大切である
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

高血圧
高血圧
→高血圧そのものにはほとんど症状がないが、脳卒中や心筋梗塞など命にかかわる重大な病気を招く、サイレントキラーである
血圧を下げる7つのコツ
1)血圧を正確に測定し、高血圧を管理する
・高血圧と一口にいっても、さまざまなタイプがある
・タイプごとにリスクや対策も変わってくる
・タイプを特定し、適切な治療を行うために、自宅で正しく血圧を測定することが大切
2)空腹の時間をつくって、標準体重を目指す
・肥満は高血圧を引き起こす大きな要因の一つである
・原料を成功するコツは、空腹を感じる時間を確保し、食べ過ぎを防ぐこと
・約3kgの減量を達成すると、降圧効果を実感することができる
3)食塩を控えて、野菜と果物をたくさんとる
・血圧を下げるためには、減塩が重要である
・自炊の場合、外食や中食の場合など、状況に合わせて無理なく減塩するポイント押さえるようにする
・野菜や果物に多く含まれるカリウムは、血圧を下げる効果が期待できる
4)「ちょいきつ運動」で高血圧の要因を解消する
・運動すると、心臓や血管の細胞が刺激され、血圧を下げるホルモンが分泌される
・このホルモンの分泌を促すためには、軽く息が弾み、汗ばむ程度のちょっときつめの運動を行うのが効果的である
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

死亡診断書と死体検案書
死亡診断書
→人の死亡の事実と、死因・死亡時刻等に関する医師の証明書
※歯科病院で、舌がん等で死亡した場合には、歯科医師も交付できる
・医師、歯科医師にとって死亡者が診療継続中の患者であり、診療されていた傷病(怪我、環境温度、中毒や病気)に関連して死亡したとき
・遺族は、役所の戸籍係に死亡届を提出する際、この書類を添付しなければならない(戸籍法第86条の2)
・死亡届が受理されないお埋火葬の許可がおりない(墓地・埋葬等に関する法律第5条)
・死亡診断書を交付されても、死因が怪我、環境温度、中毒などに関連した場合、「異常死」に該当するので、医師法第21条に基づいた警察への届け出が、別途必要となり、警察よる検視が行われ、その調査が終了するまで埋火葬を行うことはできない
死体検案書
・医師が、死体を外表から診て死因を判断すること
・医師、歯科医師にとって死亡者が診療継続中の患者であっても、診療されていた傷病と死因とが無関係の場合
・死因を調べる医師にとって、死亡者が初診の場合
・全身裸にして、視診、触診、打診や必要に応じて針を刺して尿や髄液、血液の採取などを行い、死因や死後経過時間などを判断する
・身体にメスをいれる解剖と比べれば、臓器の状態などを見ることができないので、診断制度は劣る
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

患者・被介護者の死に直面する周囲の人の心理的理解
遺される人に寄り添う際、ケア提供者が注意すべきこと
1)「がんばろう!」
・遺される人に「口先だけの励まし」との印象を与え、より一層落ち込ませるケースも多い
2)「泣いてはダメ!」
・泣くことを無理に我慢すると、心身に悪影響を及ぼすことも少なくない
・泣かないことが美徳とされがちな男性であっても、「悲しいときは素直に泣いた方がいい」と伝え、安心して泣けるような雰囲気を作ることが大切
3)「早く元気になってね!」
・「早く立ち直りたい」と願ってもどうにもならないときに、より一層プレッシャーを掛けてしまう
4)「私にはあなたの苦しみがよく理解できる」
・「何も失っていない人に私の苦しみがわかるはずがない」といったように、遺される人に反発感を抱かせる言葉となりかねない
5)「あなただけじゃない」「あなたの方がまだまし」
・ひとり一人の体験は、それぞれに唯一のものであり、決して他人と比較することはできない
・他人と比較することによって慰めようとすることは厳に慎む必要がある
6)「もう立ち直れた?」
・立ち直ってないことが悪いとの印象を与えかねないため、使用を控えるべき言葉
7)「時がすべてを癒すから大丈夫」
・死別の悲しみは、そう簡単に癒えるものではない
・たとえ長い時間が経過しても、立ち直れない人がいることを医療者、介護者は重く受け止めるべきである
8)「長い間、苦しまなくてよかったね」
・突然死の後などに、「治療生活が長い病気より、苦しみが短くてよかったかもしれないね」といった言葉を投げ掛けられると、遺族は深く傷つく
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

患者・被介護者の死に直面する周囲の人の心理的理解
遺される人が辿る悲しみの心理プロセス
第1段階「精神的打撃と麻痺状態」
・大切な人の死という衝撃的な出来事に直面し、一時的に現実感覚が麻痺状態に陥る
・一種の防御機制と考えられるが、長期にわたると健康に悪影響を及ぼす
第2段階「否認」
・理性が死という事実の受容を拒否し、「死ぬはずがない」「まだ生きるはずだ」などとの思いを抱く
第3段階「パニック」
・大切は人の死に直面した恐怖からパニック状態に陥る
・集中力が失われ、日常生活に支障をきたす場合も少なくない
・悲しみの心理プロセスの初期においては、しばしばみられる現象
第4段階「怒りと不当感」
・「不当な悲しみを負わされた」という激しい怒りの感情を抱く
・この怒りが外部に表出されずに内攻という形をとると、心身に深刻な影響を与える
第5段階「敵意とうらみ」
・周囲の人に対し、敵意やうらみという形でやり場のない感情をぶつける
・故人の不注意や不摂生が死の原因と考えられる場合、故人を責めるという形で敵意を表現する場合もある
第6段階「罪悪感」
・過去の故人への行いを悔み、自分自身を責める
・こうした罪責感の多くは論理的な根拠によるものではなく、情緒的な補償作用の一環と考えられる
第7段階「空想形成、幻想」
・空想の中で故人がまだ生きているかのように思い込み、実生活でもそのように振る舞う
第8段階「孤独感と抑鬱」
・ごく自然な反応ではあるが、周囲の人のサポートが必要になる場合もある
第9段階「精神的混乱とアパシー」
・日々の生活目標を見失った空虚さから精神的混乱状態に陥り、物事への関心を失う
第10段階「あきらめ、受容」
・大切な人、そして自分の置かれた状況を理解し、辛い現実をしっかり受け止めようとする
第11段階「立ち直りの段階」
・辛く悲しい経験を経て、新たな一歩を踏み出そうとする
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

死因の究明
司法解剖
→犯罪に関係して死亡したり、その疑いがある場合には、犯罪を立証するために死体を解剖して死因や受傷状況、死亡推定時刻等を判断するために行う解剖のこと
・日本全国一律に行われている
※「刑事訴訟法第129条」
・警察がその必要性を調査し、裁判所が必要性を認めた場合に行われており、遺族が解剖拒否の意向であっても受け入れられることはない
・解剖は多くの場合、その地域の大学医学部の法医学の部門で行われる
行政解剖と監察医制度(「死体解剖保存法第8条」)
・東京都23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市には「監察医制度」がある
・監察医は、その地域での明らかな病死以外の死体を検索し死因を判断している
・犯罪性やその疑いがあれば、遺体を大学医学部の法医学部門に搬送して大学の法医学医師により司法解剖が行われる
・犯罪性がない場合、監察医がより死因を詳しく調べる必要がありと判断すれば解剖を行うことができる(行政解剖)
・遺族の承諾は不要である
・解剖が必要と判断されるのは、検索だけでは死因不明の場合、労災の場合などである
新しい解剖システム
・行政解剖は日本の5都市でしか行われておらず、それ以外の地域では司法解剖以外に死因を詳しく調べる手段がない
・その格差を埋めるために、地域により遺族の承諾のもとに行政解剖と同じ目的で解剖を行っていた(承諾解剖)
・それに加えて、地域の警察署長が必要と認めた場合に遺族の承諾なしに解剖を行うシステムが2013年5月より始まっている
※「警察などが取り扱う死体の死因・身元調査に関する法律」
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

死因の究明
死因究明
→亡くなった原因を調べること
・病院に入院し、死亡までの経緯がよく把握されているばあいには死因の判断に困ることは少ない
・そうでない場合、死亡までの状況や場所、死体の客観的な調査や捜査が必要となる
死体検索
→医師が死体を外表から検査して死因の判断を行う作業のこと
・針を刺して尿や血液、髄液などを採取することはあるが、身体にメスを入れることはない
死体解剖
1)系統解剖
→身体の構造を知ることで医学教育や医学の進歩に役立てる目的の解剖
・亡くなった方の生前の尊い献体の意思と遺族の承諾に基づいて行われる
※「死体解剖保存法第7条、10条、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」
2)病理解剖
→病院に入院中に亡くなった方などの、病状把握や行った治療の評価のための解剖
・遺族の承諾が必要である
※「死体解剖保存法第7条」
3)法医解剖
→犯罪に関連して死亡したりその疑いがある場合、または犯罪は否定的であっても死因を詳しく調べる必要がある場合に行われる
・前者を「司法解剖」、後者を「行政解剖」と呼ぶ
・2013(平成25)年度より、「警察などが取り扱う死体の死因・身元調査に関する法律」による新しい解剖のシステムも加わっている
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

死に直面する人の心理的理解
死に逝く人の心理プロセス
第3段階:「取り引き」
・死に直面する人は、「少しでも命を延ばしてもらえるなら、人生を○○に捧げる」と、死を先に伸ばそうと「取り引き」を試みる
・取り引きの相手は、神であったり、自分の心であったり、人それぞれである
・中には、取り引きの内容を口にする人もいる
・この取り引きを数度にわたり行ったり、約束を守ることができなかったりすると、罪悪感や悩みを抱え、精神科医などによるサポートが必要となるケースがある
第4段階:「抑うつ」
・家族をはじめ大切な人との別れば迫っていることに起因する「抑うつ」の段階
・この段階においてなお、死に直面する人に「必ずよくなるはずなので、頑張りましょう」といった励ましの言葉をかけることは、非常に残酷であると言わざるを得ない
・死に直面する人の気持ちを尊重したうえで、真摯に寄り添うことが必要なのである
第5段階:「受容」
・刻一刻と迫る死に気が滅入ることがなくなるとともに、感情はほとんど欠落し、次第に長い時間眠っていたいと思うようになる
・この段階になると、家族はじめ周囲への関心が薄れていき、人と話をすることを望まなくなる
・この段階においても、家族等の中には必死に死に抵抗しようとする人がいるが、そのような姿勢は、死に直面する本人が死を受け入れることを困難にする原因となりかねない
・何も語りたくないようなら静かに寄り添い見守る、涙を流したいようなら泣いてもよいと促すなど、本人がありのままでいることができる環境を整えることが重要である
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

死に直面する人の心理的理解
死に逝く人の心理プロセス
第1段階:「否認」
・死を直視せざるを得ないとの認識を持つ反面、生きることへの望みを強く持ち続けている段階
・「死ぬのは自分ではない。自分が死ぬなんてことはあるはずがない」といった感情を抱くケースが多い
・ほとんどの人は、この段階に直面するまで、自らの死と向かい合った経験を保持しないため、死を否認しようと務める思考はごく自然なものであるとされる
第2段階:「怒り」
・近づきつつある自らの死が、動かしようのない事実であることを突き付けられ、「死ぬのは自分なのだ。間違いなく自分なのだ」と第1段階の否認を維持することが困難になる段階
・「なぜ、他の人ではなく自分が死ななければならないのだ。なぜなのだ。許せない」といった怒りの感情を抱くことが多い
・この怒りは、家族などの身近な人はもちろん、医療者、介護者を含め、ありとあらゆる人に向けられる
・それゆえ、周囲の人にとって、この第2段階は対応が難しいといえる
・死に直面する人は、怒りを表出することで、ある種の安らぎを感じるとともに、最期の瞬間をスムーズに受け入れるための準備をするとされとされている
・そのため、一見「理不尽な怒り」と思われるようなものに遭遇しても、医療者、介護者は辛抱強く彼らに寄り添うことが求められる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓


